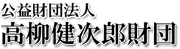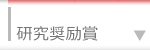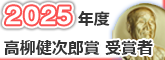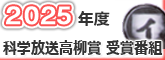研究奨励賞
2025年研究奨励賞 受賞者2 2025年研究奨励賞 受賞者1
2025年研究奨励賞 受賞者1 研究奨励賞 歴代受賞者(別ページ)
研究奨励賞 歴代受賞者(別ページ)
目的・詳細
研究奨励賞 楯
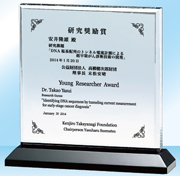
1. 目的
電子科学技術の分野で、将来の発展が期待される独創的な研究に取り組む若い研究者を表彰すると共に研究費を助成し、わが国の電子科学技術の振興並びに産業の発展に寄与することを目的としています。
2. 表彰内容
研究奨励賞 3名
表彰楯並びに研究助成金(1名当たり)200万円贈呈
3. 候補者選考
当財団が定める、選考委員会規則及び研究奨励賞選考規程に基づき、選考委員会で推薦書審査により候補者を選定し、選定候補者から提出された研究内容等を審査し、受賞候補者を内定します。
理事会の承認を経て決定し、11月下旬に結果通知を郵送いたします。
-- 選考委員会へ

●研究課題
「量子情報ネットワークに向けたダイヤモンド電子スピン-フォノンインターフェースの開発」

車 一宏博士
(東京大学 先端科学技術研究センター 助教 (工学博士) 1991年生)
量子コンピュータや量子情報ネットワークの実現は、既存の計算・通信分野に革新をもたらし、次世代の高度情報化社会 を支える重要な技術となる。そのため、それらを構成する量子情報技術の開発が強く求められている。中でも量子インタ ーフェースの開発は量子情報ネットワークの基盤技術として不可欠であり、これまで多様な量子プラットフォームの研究 が進められてきたものの、依然としてスケーラブルかつ集積可能な固体量子情報プラットフォームの実現が課題となっ ている。
本研究では、量子情報ネットワークの基幹技術として期待されるダイヤモンド中のカラーセンターを用いた電子スピン– フォノンインターフェースに着目し、固体集積型量子情報プラットフォームの基礎研究を行う。特に、ダイヤモンドに微細 加工で形成したナノ構造を活用することで、カラーセンターの電子スピンとフォノンの相互作用を高精度に制御する技 術を開拓し、量子情報ネットワークに向けた革新的な量子インターフェースの実現を目指す。
研究奨励賞 歴代受賞者(別ページ)
●研究課題
「高感度リアルタイム電界イメージングシステムに向けた微弱偏光変化検出高速イメージセンサの開発」

岡田 竜馬博士
(奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教 (工学博士) 1997年生)
Beyond5G/6Gなどの次世代移動通信では,THz波の利用が計画されている。THz波は,その指向性の高さを活 かし、局所的に電波を集中させ,混信を回避して通信を行うことが想定される.そのため,通信状況に応じて出力強度、 方向が刻一刻と変化するため、リアルタイム観察による多面的な評価が重要となる。
本研究では,電気光学(EO)結晶とイメージセンサを組み合わせて高周波電界分布を高感度かつリアルタイムに可 視化するために、高速撮像とチップ内信号処理を実現する専用の偏光イメージセンサおよびイメージングシステムの開 発を行う。EO結晶の一次電気光学効果によって生じる複屈折変化は非常に微弱である。この偏光変化を,独自に設計 した偏光イメージセンサに一様偏光子を重畳した、二重偏光子構造に基づく微弱偏光イメージングシステムで撮像する。 本システムの完成により、Beyond 5G/6Gに向けた通信状況のリアルタイムかつ多面的な評価が可能となる。
研究奨励賞 歴代受賞者(別ページ)
●研究課題
「有機薄膜デバイスにおける分極構造のリアルタイム解析と性能最適化手法の確立」

大原 正裕博士
(信州大学 工学部 電子情報システム工学科 助教 (理学博士) 1998年生)
近年、有機半導体薄膜を用いた電子デバイスは、ディスプレイや太陽電池など幅広い分野で応用が進んでいる。 しかし、真空蒸着された薄膜に生じる自発配向分極(SOP)がデバイス性能に大きく影響することが知られている にもかかわらず、その定量的評価や最適化は十分に進んでいない。大原博士はこれまでに、独自に開発した「回転 型 Kelvin probe装置」により成膜中の表面電位をリアルタイムで測定する技術を確立し、分極構造の詳細な解析 を可能にしている。さらに、蒸着を間欠的に行うことで分極の強弱や極性を自在に制御する「間欠蒸着法」を提案し、 同一材料であっても分極状態を作り分けられることを実証している。
本研究では、デバイス構造全体にわたる分極分布を評価し、電気特性との相関を明らかにすることで、性能最適 化のための定量的指標を提示する。これにより、有機 EL の高効率化や有機太陽電池・トランジスタの性能向上に 寄与するとともに、分極構造を積極的に利用した新しい動作機構を持つデバイスの創出を目指す。得られる知見は、 産業応用に直結する品質管理技術にも展開可能であり、有機エレクトロニクス分野の発展に大きく貢献することが 期待される。