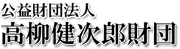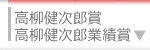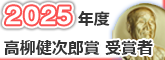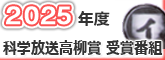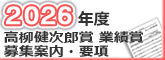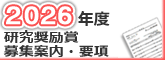高柳健次郎賞・高柳健次郎業績賞
2025年高柳健次郎業績賞 受賞者 2025年高柳健次郎賞 受賞者
2025年高柳健次郎賞 受賞者 高柳健次郎業績賞 歴代受賞者(別ページ)
高柳健次郎業績賞 歴代受賞者(別ページ) 高柳健次郎賞 歴代受賞者(別ページ)
高柳健次郎賞 歴代受賞者(別ページ)
目的・詳細
高柳健次郎賞 メダル

高柳健次郎賞 楯(▼拡大)

高柳健次郎業績賞 楯
(▼拡大)

1。 目的
高柳健次郎賞・高柳健次郎業績賞は、電子科学技術に関する優れた研究により、わが国のこの分野の振興並びに産業の発展に貢献された方々の功績に報い、電子科学技術の更なる発展とその啓蒙に寄与することを目的とした賞です。
2。 表彰内容
1)高柳健次郎賞1件 表彰楯並びに記念のメダル(18K)を贈呈
2)高柳健次郎業績賞 2件 表彰楯並びに副賞として賞金各50万円を贈呈
3。 候補者選考
当財団が定める、選考委員会規則及び高柳健次郎賞・同業績賞選考規程に基づき、選考委員
会で推薦書審査により候補者を選定し、選定候補者から提出された業績内容を審査し、受賞
候補者を内定します。
理事会の承認を経て決定し、11月下旬に結果通知を郵送いたします。
4。 候補者推薦(公募)
1)高柳健次郎賞は、次の条件を満し、人格的にも優れ、わが国を代表する指導的立場の人
・電子工学、情報通信工学及び放送工学などの分野で、特に優れた成果のあった人
・同分野で、技術や産業の発展、研究者の人材育成などに多大な貢献をした人
2)高柳健次郎業績賞は、電子工学、情報通信工学及び放送工学などの分野で、将来性ある研究成果をあげ、技術の発展や産業に貢献した人で、次世代を担うに相応しい人、 概ね、50歳以下とする。
3)候補者推薦者は、候補者が所属または関連する企業・団体等の責任者とします。
故人及び自己推薦は受け付けていません。

「直交周波数分割多重通信技術の高度化と地上デジタル放送への貢献」

高畑 文雄博士(早稲田大学 名誉教授 1949年生)
[学 歴] 1972年 3月早稲田大学 理工学部 電気通信学科 卒業
1974年 3月早稲田大学 理工学研究科 修士課程 修了
1980年 3月工学博士(早稲田大学)
[職 歴] 1974年 4月国際電信電話(株)研究所 入社
1988年 4月早稲田大学 理工学部 教授
2020年 4月早稲田大学 名誉教授
● 主な受賞等
2003年電子情報通信学会フェロー
2005年「情報通信月間」関東総合通信局長表彰
2008年「平成20年度情報化促進貢献個人」総務大臣表彰
「情報化促進部門」
2010年日本ITU協会賞 功績賞
2016年第67回 日本放送協会 放送文化賞
2017年電子情報通信学会 通信ソサイエテイ 優秀論文賞
2017年第67回「電波の日」総務大臣表彰
2018年映像情報メディア学会 名誉会員
髙畑文雄博士は、早稲田大学において、30年以上の長年にわたり、衛星通信、放送、固定通信、移動通信など 多岐にわたる分野で無線伝送技術の研究を先導し、基礎学問の観点から無線通信の発展に貢献し、特に直交 周波数分割多重(OFDM)技術の研究において大きな功績を残した。
1990年代から移動通信や放送分野での活用が検討されていたOFDM(直交周波数分割多重)技術の研究を 主導した。移動体受信環境などにおいて電波の受信レベルが変動するフェージング環境下での伝搬路推定法の 精度を高めるアルゴリズムを提案するとともに、同一チャンネル干渉下における伝送特性の改善技術の研究にも 取り組み、効率的な情報伝送と無線周波数の有効利用に貢献した。伝送する情報の信頼性と効率性を確保するために重要な誤り訂正の性能向上にも取り組み、システムの効率化にも寄与する尤度演算量の低減法を提案した。
2010年頃からはOFDMへのMU-MIMO(マルチユーザMIMO)適用の研究にも取り組み、送信側でのスケ ジューリングやビームフォーミングの効率化、伝送特性の改善により、通信性能の向上に寄与する研究を行った。 また、MU-MIMOで課題となるユーザ間干渉の抑圧に関して、高い電力効率と少ない演算量で実現できる優れ た伝送技術を提案し、その新規性と高い有効性は高く評価された。
これらのOFDM技術の研究成果は、2003年に開始した地上デジタル放送の効率的なネットワーク基盤として 生かされている。
さらに、MU-MIMOの研究成果は、無線LANや第5世代移動通信システム(5G)における通信速度の向上と 安定化、快適な無線通信環境の実現に寄与している。
OFDM技術以外の分野でも、衛星通信分野の研究を主導するなど、無線通信技術の発展に大きく貢献した。 低軌道周回衛星(LEO)について効率的な配置の導出法を提案するなど、衛星コンステレーションによる通信サー ビスの実現を見越した先駆的な研究を進めた。デジタル変復調の基礎から伝搬環境を模擬した計算機シミュレー ションの手法までを網羅的に解説した著書「ディジタル無線通信入門」は、現在でも無線通信分野を専門とする 学生や研究者らにバイブルとして愛読されている。
学会活動では、電子情報通信学会衛星通信方式研究専門委員会顧問、映像情報メディア学会会長などを歴任し 日本における無線通信技術の発展に大きく貢献した。行政機関における活動では、総務省情報通信審議会情報 通信技術分科会ITU-R部会 地上業務委員会の主査として第4世代携帯電話(4G)システムに関する日本提案の とりまとめで貢献した。そのほかにも情報通信技術分科会委員などを歴任した。
以上、髙畑文雄博士は、無線通信分野の研究に一貫して取り組み、OFDM技術の発展に貢献するとともに、 公的活動においても尽力し、放送を含む無線通信技術の発展に多大な功績を残した。
高柳健次郎業績賞 歴代受賞者(別ページ)
「テレビジョン技術の高度化に関する先駆的研究開発と実用化」

内藤 整博士
(株式会社KDDI総合研究所 取締役執行役員副所長 1971年生)
[学 歴] 1994年 3月早稲田大学 理工学部 電子通信学科 卒業
1996年 3月早稲田大学大学院 理工学研究科 電気工学専攻 修士課程修了
2006年 9月早稲田大学大学院 国際情報通信研究科 博士課程修了、
博士(国際情報通信学)
[職 歴] 1996年国際電信電話株式会社 (現 KDDI株式会社)
2010年~株式会社KDDI研究所(現 株式会社KDDI総合研究所)
超臨場感通信グループリーダー
2020年~株式会社KDDI総合研究所 執行役員(メディアICT部門担当)
2022年~株式会社KDDI総合研究所 執行役員(XR部門担当)
2025年~株式会社KDDI総合研究所 取締役執行役員副所長
● 主な受賞等
1999年 3月電子情報通信学会 学術奨励賞
1999年 9月情報処理学会 山下記念研究賞
2000年 5月映像情報メディア学会 鈴木記念賞
2002年12月映像情報メディア学会 研究奨励賞
2003年、2005年映像情報メディア学会 ハイビジョン技術賞
2009年、2011年映像情報メディア学会 映像情報メディア未来賞
次世代テレビ技術賞
2014年映像情報メディア学会 技術振興賞 進歩開発賞
2015年 5月日本ITU協会 国際活動奨励賞
2016年 6月電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ活動功績賞
2021年 5月映像情報メディア学会 フェロー
2022年12月総務省 戦略的情報通信研究開発推進事業 研究開発奨励賞
2024年 3月電子情報通信学会 フェロー
2024年 4月公益財団法人通信文化協会 前島密賞
内藤 整博士は、テレビジョン技術およびサービスの継続的な発展に寄与する独創性の高い研究開発に従事し、数多く の学術成果の創出、知的財産の確保、並びに実用化を成し遂げた。特に、テレビジョンの視聴デバイスが進化しテレビジョ ンの視聴スタイルが多様化していく中で、視聴者に驚きや感動を与えられるテレビジョン技術の確立を目指し、これまで革 新的な取り組みを主導してきた。
具体的には、①超高精細映像符号化技術の開発と実用化、②通信・放送連携ワンセグ携帯端末の開発、③自由視点 映像技術の開発と実用化において、以下のとおり、学術界・産業界に多大な貢献を果たした。
① 超高精細映像符号化技術の開発と実用化:現在、インターネット動画として一般的に活用されているハイビジョンや 8K 放送などで展開されているスーパーハイビジョンを対象とした超高精細映像符号化技術の開発において、数多く の功績を残している。8K の実用化試験放送が開始された2018 年よりも10 年前から、8K 放送に必須となる 超高精細映像符号化技術の研究開発を推進し、国際標準方式ITU-T H.265/MPEG HEVC や、同方式をマルチ アングル映像向けに拡張したMPEG MV-HEVC の規格化において多くの技術を提案した。2017年には本規格に 準拠したリアルタイムコーデックの開発に成功し、8Kマルチアングル映像のリアルタイム伝送を実現した。
② 通信・放送連携ワンセグ携帯端末の開発:現在では極めて身近となった、スマートフォンや携帯端末による動画視聴 サービスについて、その黎明期を支えた携帯電話向け通信・放送連携サービスの視聴を可能とするワンセグ携帯端末 の開発に携わった。具体的には、通信回線を利用したインタラクティブなコンテンツ連携処理を携帯電話の極めて限ら れた計算リソース上で行う端末実装技術をもとに、ワンセグ放送に対応した携帯端末を世界に先駆けて開発した。 この実績はその後の携帯電話などにおけるワンセグ対応端末の市場展開に大きく貢献するとともに、現在では一般的 となっている、スマートフォンによる動画視聴スタイルの礎を築いた。
③ 自由視点映像技術の開発と実用化:没入感を追求したテレビジョンサービスの実現に向けて、スポーツイベントや 音楽ライブなどで視聴者自身が好みの視点から映像を楽しむことが可能な、自由視点映像技術の開発に関わる成果 を創出してきた。自らが考案した技術によって撮影条件の制約が大幅に緩和され、クロマキー撮影やカメラ操作が制 限された状態での撮影など、厳しい条件を受け入れ難いスタジアムなどの屋外大空間での応用を可能にした。スポー ツ中継でのリプレイ放映を目指したトライアルを重ねることで、画質と速度の両面において完成度を飛躍的に高め、そ の成果として制作された自由視点映像が地上デジタル放送の番組に活用されるに至った。加えて、同技術をスマート フォン向けの映像サービスに活用し、プロ野球の試合では5G(第5 世代移動通信システム)の回線を利用した映像配 信実験に成功し、Jリーグ公式戦ではスタジアム観戦の体験価値を向上させるツールとして商用導入された。
以上のとおり、内藤整博士は、テレビジョンの多様な視聴スタイルに応じた革新的なテレビジョン技術の研究開発と国際 標準化を進めると共に、実証システム開発および商用展開を通じてテレビジョンサービスの発展に寄与した。

山崎 俊彦博士
(東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授 1976年生)
[学 歴] 1999年 3月東京大学 工学部 電子工学科 卒業
2001年 3月東京大学 工学系研究科 電子情報工学専攻 修士課程 修了
2004年 3月東京大学 工学部研究科 電子工学専攻 博士課程 修了、
博士(工学)
[職 歴] 2004年~2006年東京大学 大学院新領域創成科学研究科 助手
2006年~2009年東京大学 大学院情報理工学系研究科 講師
2009年~2022年東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
2011年~2013年米国コーネル大学 客員研究員(Visiting Scholar)
2022年~現在東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授
● 主な受賞等
2007年 3月電子情報通信学会学 術奨励賞
2009年 5月映像情報メディア学会 丹羽高柳賞論文賞
2017年 2月船井情報科学振興財団 船井学術賞
2023年 3月電気通信普及財団賞(テレコムシステム技術賞)
2025年 6月ACM ICMR Best Paper Award
「魅力工学」とは、人の感性・共感などの主観的な嗜好・判断を計算科学的に分析し理解・再現することをコンセプトと する研究領域であり、山崎博士が名付けた研究である。魅力工学の英名である”attractiveness computing” は、 Bing 検索で0 から548,000 件もヒットする新たな概念となっている。
1. 人のコミュニケーションの評価・分析に関する研究
人と人とのコミュニケーションやメッセージ発信を評価し、向上のためのフィードバックを行う研究を世界に先駆けて
行った。マルチモーダル分析によるオーラルプレゼンテーションの印象予測では、プレゼンテーションが聴衆に与える印象
を説得力、印象度など14 種類の尺度で評価し、時系列的な改善ポイントを示すことを可能とした。技術的新規性は、時に
は1 時間以上にも及ぶ膨大なテキストや音声を分析可能にし、2つのモダリティを効果的に扱える学習モデルを提案した
点にある。この研究は、その後、オンライン面接における人材評価 、記者会見トレーニング 、チャットシステムにおける精神
疾患の見極めや改善支援など様々な分野へと発展した。
2. SNS における人気獲得に関する研究
SNS の人気獲得のメカニズム分析について、国際的に先駆的な研究を複数行った。SNS の閲覧数やいいね数を social
popularity score と定義して分析する研究は、博士が提案した研究領域であり、Bing 検索では1 万件以上ヒット
する概念となった。現在でも、博士の論文が一番上に掲載される。SNS の人気を分析するだけでなく、ハッシュタグ推薦
によって人気度を向上させる技術を世界で初めて提案し、SNS 上での実投稿実験で閲覧数を2.5 倍以上に増やせる
ことを示した。この成果は国内外のメディアで大きく取り上げられた。これらの研究成果は、複数の企業にライセンス提供
され、社会実装に及んでいる。
3. 多彩な異分野連携・産学連携
学術的に最先端であるだけでなく、有機的な産学連携・社会還元につながっている。 通算で40社以上との共同研究、
15 件以上の知財のライセンス提供 (いずれも2025 年9 月現在)を行っており、複数の実サービスへと発展した。
これらの過程で博士研究員および博士課程学生25 名以上の育成も行った。さらに、広告・デザイン・PR・不動産などに
おいて魅力工学に関する問題意識を共有する様々な領域の研究者らとのコミュニティの構築・発展にも尽力し、国内外で
研究会や国際ワークショップの立ち上げを先導した。
このように、候補者は学術的に新しい課題を定義し開拓しただけでなく、コミュニティの構築と先導、研究成果の社会還元
を行うなど、情報通信分野の学術への貢献が目覚ましい。